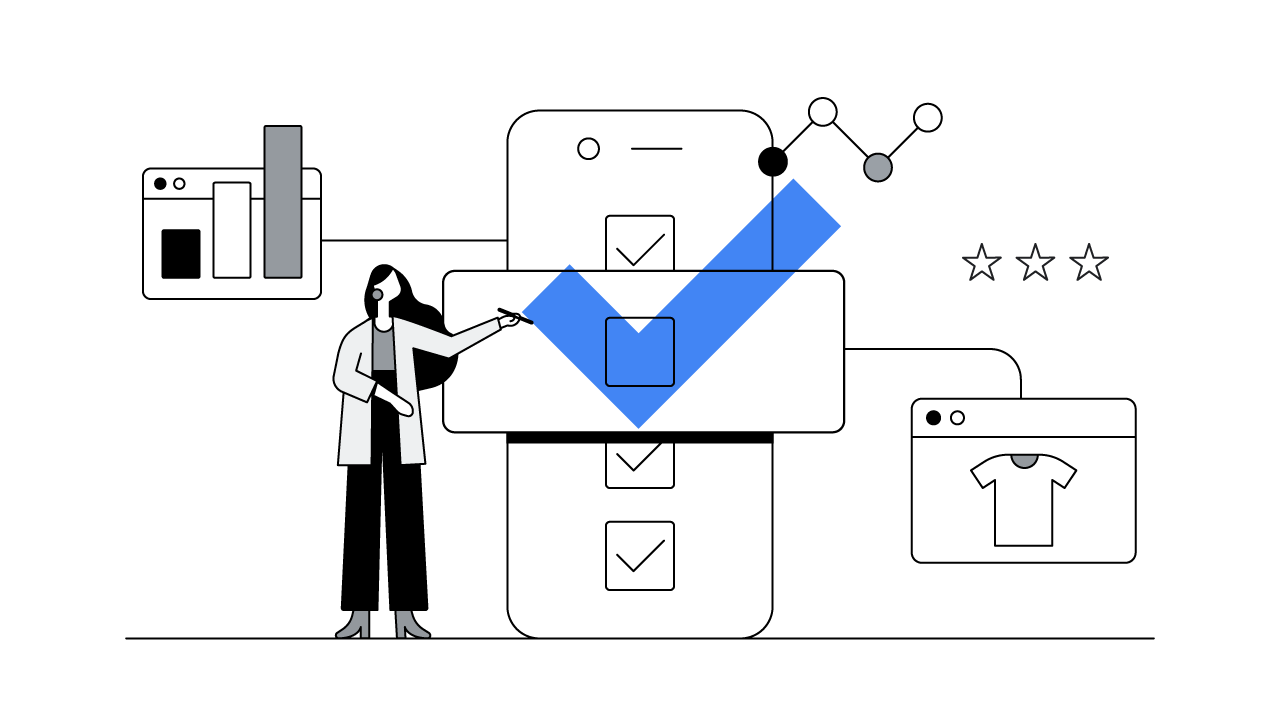ビジネスにおける「マーケティングリサーチ」という概念のアップデートを目指す本連載。前回は定量調査について、その役割や経営判断に不可欠だが見過ごしがちな問題をお伝えしました。連載第4回となる今回は、定性調査についてお話しします。定性調査から適切なインサイトを得て、ゲームチェンジをするには、どういった視点が必要なのでしょうか。
定性調査の評価が分かれる理由
マーケティング活動の中で、定性調査ほど人によって評価が変わる調査手法はないでしょう。定性調査で発見されるインサイトこそマーケティング戦略の決め手だという人もいれば、N 数(サンプルサイズ)が少な過ぎる(=代表性がない)ことで、「この結果だけでは戦略は決められない」と言う人もいます。私自身、「面白いね。でもそれって N いくつ?」と言われて、調査レポートが閉じられる場面をよく目にしてきました。
定性調査がこのような扱いを受けるのには、いくつかの背景があります。その 1 つが、インターネットパネルの登場により定量調査が極めて安価にできるようになったことです。
それまでは、定量調査は定性調査よりもずっとコストのかかる調査手法でした。サンプルの代表性を担保するために、各地域の住民台帳をもとに 1 軒ずつ訪問する、調査票を郵送する、機械でランダムに選んだ電話番号に調査依頼をかける、あるいは、街中で対象の人に声をかけて回答してもらう……これらを一定数以上の回答が得られるまで続けるしかなかったのです。
もちろんこうした手法は、国勢調査をはじめ今でも広く使われていますが、今ではインターネットを使った調査が一般的になりました。それに伴い、「調査」というとインターネットを使った定量調査をイメージする人が増え、その結果、本来目的の異なる定性調査でも過剰に N 数を気にする傾向が強くなったのではないでしょうか。
「定性調査で結論づけることはできない」「仮説は必ず定量調査で証明できなければならない」といった声を聞くこともありますが、実は回答者の顔がある程度想像できるのであれば、定量調査よりも、条件を満たす何人かの人に聞きたいことをインタビューする定性調査の方が適していることもあるのです。
聞けなかったことの中にこそ答えがある
定性調査の評価が分かれるもう 1 つの理由は、現場で聞いたことがそのまま結果になる訳ではなく、むしろ聞けなかったことの中にこそ答えがあるという点があります。
たとえば以前、オンラインショッピングにおける消費者のインサイトを探るために、実店舗と EC サイトでの普段の買い物の実態を調査したことがあります。さまざまな家庭を訪問し、普段の買い物についての考えを聞き、さらに実店舗で買うものと EC で買うものを聞いたうえでその両方の買い物に同行するというものでした。
ある女性に話を聞いたところ、EC では趣味のアロマテラピーに関連するものは買うが、一般消費財の買い物では EC を利用しないと答えてくれました。理由は、いつもの店で実物を見て買い物をしたいからとのことでした。もちろんそれは本心だったと思いますが、その後スマートフォンで EC サイトの閲覧履歴を見せてもらったところ、柔軟剤や消臭剤などを時折 EC で購入していることがわかったのです。
この人は嘘をついたのでしょうか。そうではありません。このズレが生じた理由の 1 つは、私たちが「普段」と聞いたことでした。つまり、この女性にとって「時折購入する柔軟剤や消臭剤」は「普段」の買い物ではないという認識だったのです。そしてもう 1 つの理由は、彼女は消費財の購入を EC で済ませることに対して、無意識のうちに罪悪感があったためです。 このため買い物行動の記憶にふたをしていたのです。
これがまさに「聞けなかったことの中にこそ、答えがある」ということです。定性調査だからこそ、この女性の話を深掘りでき、オンラインショッピングで済ませてしまうことへの罪悪感に気づくことができました。そして結果的に、この罪悪感はその人特有のものではないこともわかりました。
このように、対象者も意識していなかった認識があれば、結果にズレが生じる可能性があります。この意識と無意識のズレを理解することがマーケティングリサーチの重要な課題であり、そのために実施するのが定性調査なのです。
定性調査に N 数を求めることは意味がない
またマーケティングリサーチのインタビューでは、対象者が質問を受けた時に最初に想起する回答は、本人の考えではなく、世の中に広く流布しているアイデアや、その場をリードしている人の意見に同調しようとすることが多いことが、経験的にわかっています。
たとえば以前の調査で、ある商品の動画広告を見てもらい、「この CM を見たことがあるか」「見たことがある場合、どこで見たのか」を質問をしたことがあります。すると回答者の 20% 程度が「テレビで見た」と答えました。しかし実はその広告は、オンラインのみでの配信で、テレビでは類似のものも含めて一切流れていなかったのです。
これは、人が持つ認知バイアスによるものです。つまり「この CM は見たことがある。普段このような動画広告を見るのは大体テレビだ。そうであればこれもテレビで見たのだろう」と考え、誤った回答をしてしまうのです。一般的にこの手のバイアスは過去の経験量に比例して強まります。テレビ CM のように子供の頃からずっと見続けてきたものの場合、オンライン上での動画広告に比べてよりバイアスが強くなり、誤回答されやすくなるのです。
そして、この問題をややこしくさせるのは、こうしたバイアスがかかった回答は、異なる多くの人から出てきやすく、つまり誤回答でありながら、N 数を稼ぎやすくなるということです。そして、このような誤回答は認知バイアスが原因ですから、定量調査でも定性調査でも生じるのです。さらに調査の受け取り手であるマーケティングリサーチャーも同じようなバイアスを持っているので、自分の予想の範囲内にあるそうした回答に飛びつきやすくなってしまいます。前回の定量調査の説明で取り上げた「無意識のバイアス」とも関連しますが、リサーチチャー自身が仮説に対して持つバイアスが誤った結論を導くことにつながってしまう可能性があるのです。
しかしマーケティングリサーチにおける定性調査は、それではダメなのです。定性調査は多くの人が同じように答えるだろうことを確かめるための手法ではありません。暮らしぶりや直面する問題はそれぞれ違うものであり、個人レベルでの行動や言葉も違うことは当たり前です。ですから定性調査に N 数を求めることには意味がありません。それどころか数だけを求めてしまうと、本来掘り出すべきインサイトを見逃してしまうのです。
定性調査からゲームチェンジを起こすには
とはいえ「1 人 1 人違います」という結論で調査を終わらせることもできません。リサーチャーが観察した対象者の行動や言葉は違えど、その背景にある共通性を見つけるために適切なプロセスを踏むことで、良質なインサイトを得られる定性調査になります
この役割を担うのは、定性調査を実施したリサーチ会社だけではありません。依頼主でもあるマーケティングリサーチャーや、ブランドマネージャーなどさまざまな視点を持つ何人もの人がそのプロセスに立ち会う必要があります。対象者との対話から集めた情報や、自分自身のマーケティングリサーチャーやブランドマネージャーとしての経験や学び、これまで担当した商品やサービスのコミュニケーションやプロモーションのあり方、競合との関係性、あるいは関連する別の調査結果やその時の社会情勢など、すべての情報を惜しみなく共有しながら、その言葉や行動の背後にある「なぜ」を探っていかなければなりません。
こうした過程を経ることで、個人のインサイトの集まりが徐々に、何らかの共通の属性があるグループ(デモグラフィック、ソシオグラフィック、サイコグラフィックあるいはそれらの組み合わせ)の共通のインサイトへと昇華されます。場合によっては、社会全体に共通するインサイトの発見につながることもあるのです。逆にいえば、本来インサイトとはそうしたプロセスを経なければ見出すことはできないものなのです。
ですから、そのプロセスを経ていない “ インサイト ” は、すでに世代論などを通してマーケットで語られている常套句の再生産でしかありません。それではマーケットを変化させること(ゲームチェンジ)はできないのです。
もしあなたが、インサイトをもとにゲームチェンジングな戦略を作りたいと考えて定性調査をするなら、インタビューの発言録と、その場の写真が貼ってあるパワーポイントを眺めているだけでは足りません。
自分自身がマーケティングのプロフェッショナルとしてその発掘に参加し、自ら気づき、発見しなければなりません。そうしたマインドセットがあれば、定性調査において N 数や代表性に囚われることはなくなるはずです。